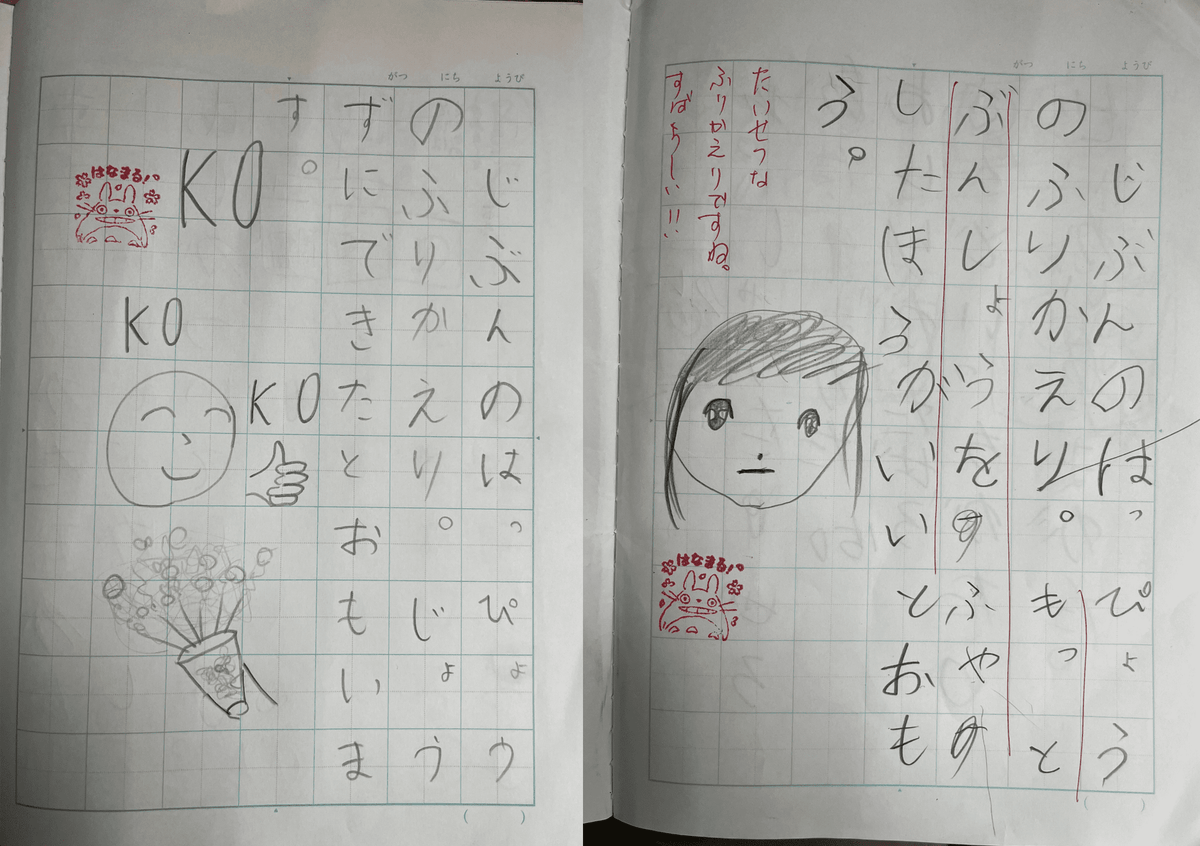
1年生が楽しんで活動する国語授業 -「はたらく乗り物を紹介しよう」-
|
執筆者: 青木 伸生
|
目次
なんでも初めての取り組みになる1年生。子どもたちの意欲はなかなかのものです。 その意欲を失わないようにするのが教師の役目。
しかし、「きちんとさせよう」という思いが強すぎると、楽しむはずの言語活動は、教師からの「注文の多い料理店」になってしまい、子どものせっかくの意欲が失われていきます。子どもたちが困ると、教師はそのサポートに忙しくなり、教師自身のゆとりも失われます。
まずは、子どもの「やってみたい」気持ちを最優先にして、等身大の言語活動を設定しましょう。今ここで、この単元で達成できなくてもいい部分は目をつぶり、言語活動を経験することに重点をおきます。1年生の子どもたちは、これから6年間という長い時間をかけて、様々な言語活動を経験し、成長していきます。そうした見通しの中で、言葉の学びとして何を大切にするかをよく考え、実践していきましょう。
1年生の2学期の単元として、子どもも教師も大変にならない学習活動を紹介します。
