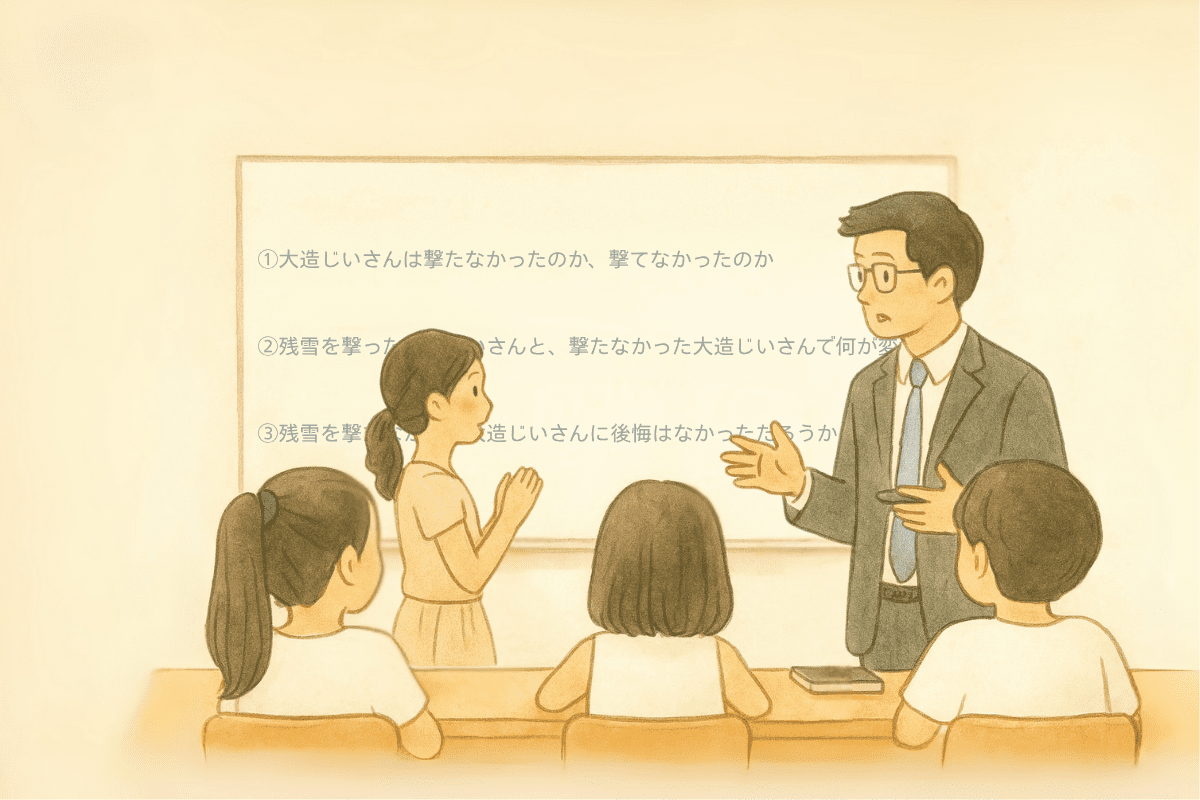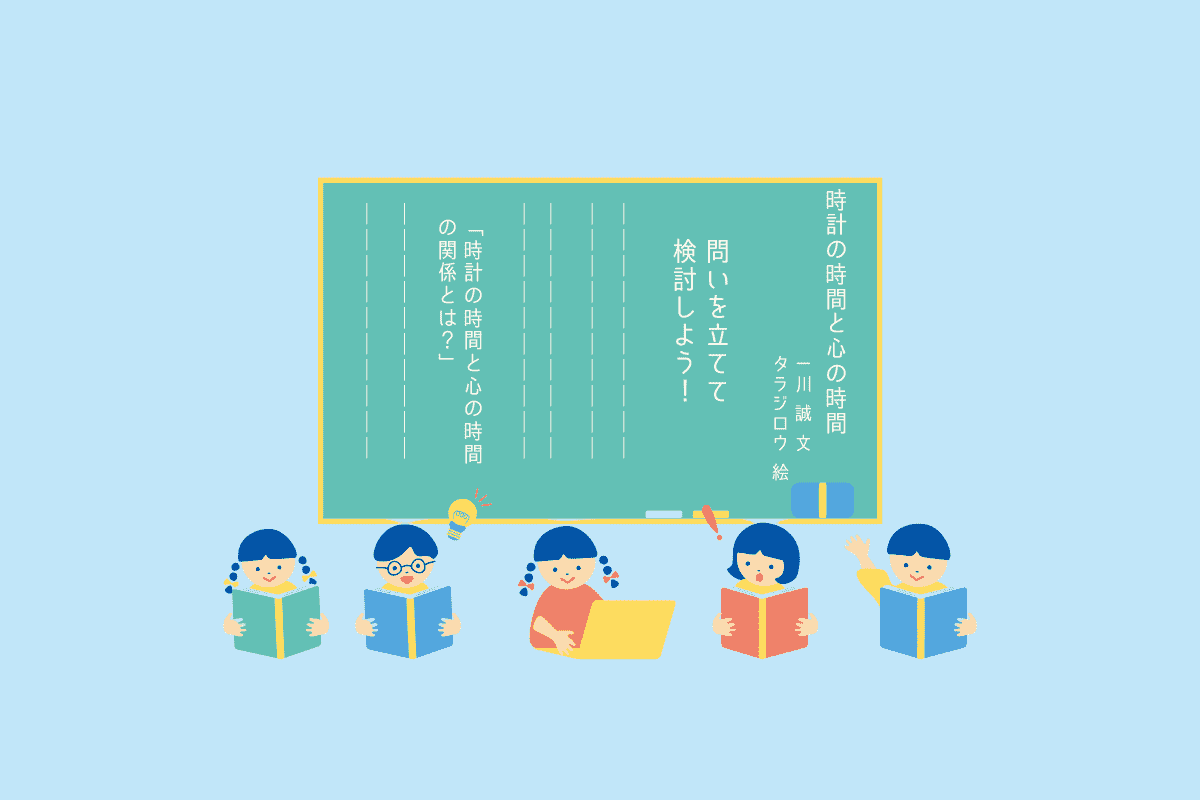子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
国語科授業における発問づくり
―3つの視点から問う―
発問は、教師の「教える」と子どもの「学ぶ」を合致させる授業展開の要です。 発問をどのようにつくっていくか。 これまで、それぞれの経験や感覚に依るところも多かったといえます。 今回は、物語を例に、発問づくりに焦点を当てて、どこを、どのように発問するかについて、一緒に考えていきましょう。 そこで、本稿では、「時計の時間と心の時間」(光村図書・6年)を例に、問いを立てる場面で大事にしたいポイントを紹介します。その上で、決まった問いで、どのような読み合いが展開されたのかを紹介します。
![]() 有料記事
有料記事
説明文におけるリフレクション型国語科授業の展開
-「時計の時間と心の時間」(光村図書・6年)を例に-
リフレクション型国語科授業の授業原理は、「問いを学習者である子どもが決める」ことです。では、説明文で問いを立てる際のポイントはどこにあるのでしょうか。それは、問いをどこに向かって立てていくのかに関わってきます。 説明文の場合、問いを「筆者」に向けて立てていきます。説明文の内容も、述べ方も、主張も、それを束ねるのが筆者です。筆者に向けて問いを立てていくことで、読むことが機能するといえます。 本稿では、「時計の時間と心の時間」(光村図書・6年)を例に、問いを立てる場面で大事にしたいポイントを紹介します。その上で、決まった問いで、どのような読み合いが展開されたのかを紹介します。
![]() 有料記事
有料記事
リフレクション型国語科授業の展開
-立てた問いでの読み合い、その授業展開-
リフレクション型国語科授業は、「問いづくり →読み合い →問いの評価」を位置づけて展開しています。 前回は、物語「ごんぎつね」を例に、どのように問いを立てていくのか、「問いづくり」に焦点を当てて授業展開を紹介しました。具体的に、「問いづくり」の授業の実際と、そこでの教師の関わりについて、知っていただけたかと思います。
![]() 有料記事
有料記事
リフレクション型国語科授業の展開
-問いをどのように立てていくか、その授業展開-
これまでの国語科授業は、「教師による発問・応答型の授業」と言われるように、教師が発問することによって、子どもは発問に対する正解や最適解を導き出していくものだったといえます。
![]() 有料記事
有料記事
リフレクション型国語科授業の展開
リフレクション型国語科授業は、学習者である子どもたちによる「問いづくり→読み合い→問いの評価」を位置付けて展開しています。これまでの国語科授業では、主に教師の発問によって、思考の文脈が形成されていました。言い換えると、子どもたちは、教師の発問に対する答えを探す営みをしていたといえるでしょう。その姿は、どこか受動的でもあります。